
本記事はポッドキャスト番組「イケジンRadio」の内容を記事化したものです。
 やまけん
やまけんイケてる人事情報をお届けする「イケジンRadio」へようこそ!現役人事担当の「せやまん」と「やまけん」がお届けします。
この番組では、注目の人事施策やチャレンジングな取り組み、人事担当者の学びになる書籍など、現場で奮闘されている人事担当者の方や経営者の皆様に向けて、リアルな人事情報をお届けしています。
よろしくお願いします!



さて、本日の語り合いたいテーマですが「血の通った組織とは?」について対話させてください!
音声で聴きたい方はこちらから
「血の通った組織」とは?人事担当者が考える定義



血の通った組織…。人事としてはめちゃくちゃ興味深いテーマです!



そうですよね。やっぱり人事としては「人が本気で働ける組織」を作っていきたいと思ってるんですよね。
人が本気で働ける組織=血が通っている組織なのではないかと考えてます。



社員のやる気を上げていこうと考えると、立派な人事制度やオシャレなオフィス、充実した福利厚生が必要なんじゃないかとか考えがちですよね。
もちろん、それらも重要だとは思いますが、それ以上に必要なのは「働く人の心を動かす」ことだと私は考えています。
「自分はここにいていいんだ」「誰かがちゃんと見てくれている」「自分の存在に意味がある」と感じられるような組織が、まさに「血の通った組織」なのではないでしょうか。



おっしゃる通りですね!人と人とのコミュニケーションが大切にされていたり、心が通い合う仲間としての繋がりがしっかり感じとれる組織は仕事をする上で理想的な組織だと思います。
機械的ではない、人の温もりを感じる働き方



ええ。「自分のタスクだけをこなして終わったら帰る」「会話もないまま業務が進む」といった働き方では、あまりにもドライで機械的になってしまいますよね。
それは、いずれChatGPTなどのAIに取って代わられる可能性のある仕事になってしまうかもしれません。
職場や仕事にこそ、人の温もりが必要だと感じています。



めちゃくちゃ深いテーマですね。
それが「血の通った組織」ということなんですね。



そうです。誰かに見られている感覚、ちゃんと評価されている感覚がないと、「自分は何のためにこの仕事をやっているんだろう」となりがちですからね。



確かに。そういった意味では、「血の通った組織」というのは、多くの企業が目指すべき理想の姿かもしれませんね。
人が本気で働くために必要な具体的な要素と心理的安全性



血の通った組織を作る上で私が重要だと考えているのは、チームとして業務を行う中で、誰かが困っていたら自然と声をかけたり、ミスをした時に「大丈夫だよ」と励まし合ったりすることです。



また、アイデアや意見を立場に関係なく自由に言い合えたり、上司と部下の関係が指示だけではなく、人と人として繋がっているような会話があったり、感謝や称賛をきちんと言葉で伝え合っている。
そんな職場こそが、まさに血が通っている組織だと感じています。



いわゆる「心理的安全性」のある組織でもありますね。
こういったコミュニケーションって大切だと言われていたり、当たり前だという感覚はあるものの、意外と軽視されていたりするかもしれませんね。



そうなんです。意外とこれは意識しないとできないことだと思うんです。
自分の業務で手一杯になると、他のメンバーのことまで見えなくなってしまうこともあります。
しかし、そんな時でも困っている人がいたら声をかけられるような、相互の助け合いができれば、それは血が通っている組織と言えるのではないでしょうか。



よくある同調圧力のように、「こんなことを言ったら気まずくなるんじゃないか」「怒られるんじゃないか」といったことを気にすることなく、安心して自分の意見が言える。
上司も部下をきちんと見ていて、指示だけでなく、部下と上司が人と人として繋がっている。
こういう組織なら安心して仕事に集中できますよね。
意図的に「いつでも話せる空気」を作る



効率を重視すると、人と対話することが面倒に感じたり、非効率に感じられる場面もあると思います。
しかし、そういった手間をかけるからこそ、相手のことが理解できるようになったりしますし、コミュニケーションを大切にしたカルチャーが育まれていくと思うんですよね。



なるほど。確かにコミュニケーションをとろうと誰もが思っていると思いますが、「邪魔してはいけないな」「今忙しそうだから後で話しかけよう」と考えて、結局チャットで済ませてしまう。
それを続けていると、一日を終えてみれば大した会話をしていなかった、ということも少なくないかもしれません。



だからこそ、「いつでも聞いていいよ」といった空気感を、意識的に皆で作っていく必要がありますね。そして、それは一人だけでは作れません。
やはり、チームの皆がそういった意識を持たないと、血の通った組織は生まれないと感じています。
自分だけが意識して積極的に話しかけても、周りが「忙しいんで」といった雰囲気では成り立ちませんからね。めちゃくちゃ大事ですね。



組織として「私たちはこういうコミュニケーションを大切にしています」と明言することも重要かもしれません。
例えば、経営層からも「人の温もりや温度感を感じる瞬間を意図的に作っていこう」といったメッセージを発信し、コミュニケーションが阻害されないような取り組みをビジョンなどに盛り込むのも大切ですよね。



会社全体からそういったメッセージがあれば安心ですね。
ちょっとした気遣いや、サービス精神、ホスピタリティといったものを皆が忘れなければ、組織は格段に良くなる気がします。



そうですね。あと、長く働いていけばいくほど、周りとの関係がなあなあになってしまって、「言わなくても分かるだろう」といった気持ちから、コミュニケーションが疎かになっていくことってありますよね。
これは、おそらくどの組織でも起こりうることだと思います。
心が通いあうようなコミュニケーションを皆が意識できるようなカルチャー作りを、人事も積極的に行っていかなければならないと感じますね。
ポジティブな感情がもたらす効率アップとネガティブの影響



「機嫌が良い・悪い」といった個人の感情も、組織に大きな影響を与えると考えています。
心理学でいうと、機嫌のいいポジティブな人が集まると生産性が上がるらしいです。
通常の機嫌を1して、通常より機嫌の良い1.1の人たちが集まることで、全体の生産性が33%上がるというデータがあるそうです。
逆に、機嫌が少し悪い0.9の人たちが集まると、生産性が27%ほど落ちるというのです。



おぉ、そんなに人の機嫌が全体を左右するんですね。。



さらに恐ろしいことに、機嫌の悪い人が3人集まったグループに、機嫌の良い人を含む別の3人が加わって計6人になったとします。
すると、機嫌の悪い人の雰囲気に引っ張られてしまい、全体の生産性が9%ほど下がってしまうらしいのです。



悪い機嫌が、そこまで大きなパワーを持ってるとは。確かに機嫌が悪くてピリピリしてる人がいると、その人の言動が気になったりして仕事に集中できなくなりますよね。



だからこそ、いかに皆が機嫌良く働けるチームを作るか。それが、血の通った組織に繋がる一つの要素になるのではないでしょうか。
雰囲気が良ければ効率が上がる一方で、ネガティブな人がいるとそれに引っ張られてしまう。それが非常に良くない状況を生むのです。



人間のデフォルトはネガティブだといいますからね。ネガティブな感情に引っ張られやすいという感覚はよく分かります。



ですから、採用の段階でなるべくポジティブシンキングな人を採用し、そういった人材を育成していきたいですよね。
しかし、そういう人でも、もしかしたらネガティブな雰囲気の部署に配属されてしまうと、その空気に染まってしまい、パワーが落ちてしまうということもあり得るわけです。
なぜ組織に雰囲気を変えるリーダーが必要なのか



だからこそ、雰囲気を変えることができる「キーマン」を各部署で作っていく必要があると思います。
サッカー日本代表の長友選手が数年ぶりに代表に復帰した際のニュースで、森保監督が話されていたのですが。
アジア大会の準決勝で負けた際に、日本の悪い部分が出てしまったそうで、それは「雰囲気を変えられる人材」がいなかったらしいんですね。
その後、日本の雰囲気を変えられる選手が必要だと考えて、あの長友選手を意図的に招集したそうです。
長友選手は非常にポジティブですし、雰囲気をガラッと変えてくれる印象がありますよね。



確かに!長友選手といえば「ブラボー!!」ですもんね!



はい(笑)やはり、長友選手のように太陽のような元気さで、雰囲気を打破できるキーパーソンがチーム作りには必要不可欠なのだと思います。
「血の通った組織」実現に向けた人事の役割



そして、人事もまたポジティブな存在として、雰囲気が悪い時にそれを変えられるような声かけや仕組みを作っていく必要があります。
まずは部署に一人ずつでも、そういった仲間を増やしていくことで、会社の雰囲気がガラッと変わるのではないでしょうか。



そう考えると、人事担当者自身も空気や雰囲気を変えていける、ポジティブな存在でいる必要があるということですね。
その上で、組織全体を見て、ムードメーカーのような人材を発掘・育成していくことも考えておく必要がりますね。



そういった意味で、「血の通った組織」にしていくために、人事が組織の中で何をすべきか。これは私たち自身も深く考えていかなければいけないテーマですね。



まずは自分自身が組織の血を巡らせる存在になれるように、あらためて場づくりからトライしていこうと思いました!
今回の血の通った組織というテーマ。とても良い話ができたと思います!ありがとうございました!
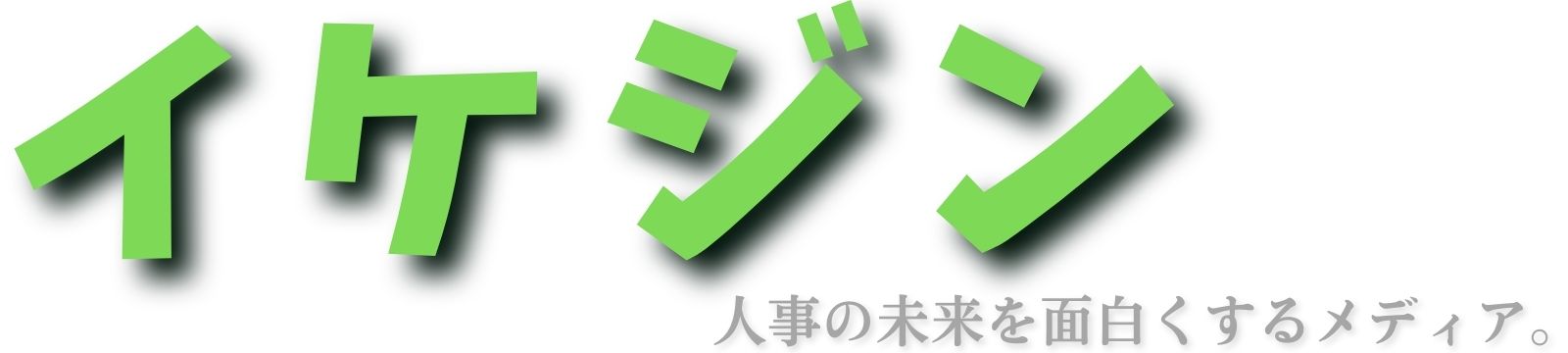

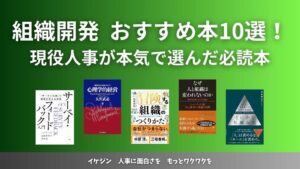
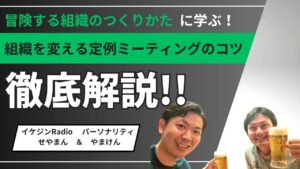


コメント