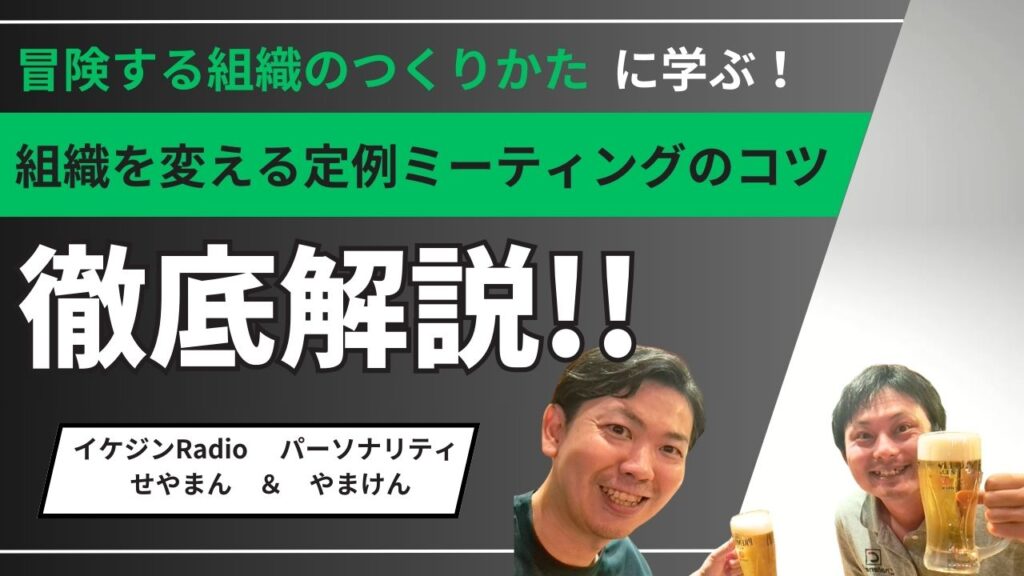
本記事はポッドキャスト番組「イケジンRadio」の内容を記事化したものです。
 やまけん
やまけんイケてる人事情報をお届けする「イケジンRadio」へようこそ!現役人事担当の「せやまん」と「やまけん」がお届けします。
この番組では、注目の人事施策やチャレンジングな取り組み、人事担当者の学びになる書籍など、現場で奮闘されている人事担当者の方や経営者の皆様に向けて、リアルな人事情報をお届けしています。
よろしくお願いします!



よろしくお願いします!
音声で聴きたい方はこちらから
話題の書籍『冒険する組織のつくりかた』から学ぼう!





さて、今回はですね、人事本の紹介コーナーです。
今話題になっている書籍『冒険する組織の作り方 軍事的世界観を抜け出す5つの思考法』を参考にして「組織づくり」について語り合いたいと思います。



皆さんもう読まれましたか?かなり話題になってましたよね。



そうなんですよ。人事の方、経営者の方、マネージャーの方など、多くの方が注目していますよね。



ええ、僕も早速購入しましたが、タイトルからしてもう惹き込まれますよね。「軍事的世界観を抜け出す5つの思考法」って気になりすぎる!



めっちゃいいタイトルですよね!書籍の内容も素晴らしいですが、「軍事的世界観」というワードが衝撃的でした。
普段は特に意識していなかったけれども言われてみると「あの会社のカルチャーは軍事的世界観だったのかも」と気付かされることが本当に多かったです。



確かに、使われている用語一つとっても、会社のカルチャーが出ますよね。
ターゲット、ペルソナといったビジネス用語の中に、軍事用語が含まれていたという発見は大きかったです。



まさしくですね!読み進めるうちに、これまで所属していた会社はどうだったんだろう、と振り返る良い機会にもなりました。
本書は、軍事的な組織をただ否定しているわけではなく、多様な考え方があることを示しつつも、現代のような変化の激しい現代においては、冒険する組織の方が個人のアイデンティティを発揮しやすいといった視点がとても共感できる内容でしたね。



そうなんですよね。全否定ではなく、様々な考え方がある中で、今の時代にどうバランス良く焦点を当てていくか、という視点が示されているのが素晴らしいと思います。
人事の方であれば、ぜひ一度手に取っていただきたい一冊ですね。
ちなみに、この書籍紹介は完全に僕たちの自主的なものでして(笑)。
宣伝ではありませんので、念のためお伝えしておきます!



さすがです(笑)。本当に、私たちがお金をもらっているわけでもなく、純粋に良いと思ったからご紹介しているチャンネルだということを強調しておきたいですね。
お金の匂いは一切ありません!
日々の「定例ミーティング」の質を底上げしていこう





さて、今回は『冒険する組織のつくりかた』の中から、意見交換したいポイントがあります。
298ページに書かれている「日々の定例ミーティングの質を底上げする」という部分です。
定例ミーティングは、様々な組織で行われていると思いますが、定期的に行われているからこそ、その質を高めることは非常に重要ですよね。
今回はここに焦点を当てて、議論を深めていければと思っています。



ぜひお願いします。



はい。まず書籍から、定例ミーティングに対する考え方についての引用部分をご紹介します。
定例ミーティングは組織カルチャーを映し出す鏡です。逆に言えば、日々の会議こそが組織作りにおけるレバレッジポイントです。
特別な施策を講じたり、高価な研修をやったりするくらいなら、まずは日常的に繰り返し行われる定例ミーティングが普通に徹底的にこだわったほうが、組織の冒険度はよほど確実に高まります。



なるほど。確かに、週に一度など定期的に行われる定例ミーティングは、定例であるがゆえに、なんとなく形骸化してしまっている会社も少なくないかもしれませんね。



この引用にあるように、定例ミーティングの質を上げていくことで、生産性や社員エンゲージメントの向上に繋がる可能性は大いにあると思います。今日はこの点を深掘りしていきましょう。
よくあるダメな定例ミーティングとは?





本書の中には、ダメな定例ミーティングの事例が4つほど挙げられていましたよ。



気になります!ぜひ教えてください。



はい!まず1つ目です。
「やたらと出席者が多いオンライン会議。しかし、ほぼすべてのメンバーがビデオとマイクをオフにしており、一部の幹部クラスが一方的に話すだけ。」



あー、これはありがちですね!画面オフ、マイクオフでチームリーダーだけが話す、みたいな光景は見られることがありますよね。



確かに、全社定例など人数が多い場合は仕方ないですが、5、6人程度の定例ミーティングで、ほぼ画面もオフというのは、あまり良くないですよね。
一方的な発信になってしまいがちです。



ええ、リーダーだけがずっと話している状況は、メンバーにとっても受け身になってしまいますからね。



本当ですね。続いて2つ目です。
経営リーダーが厳しい調子で自論を語っている会議。社員たちは資料に目を落としながらじっと聞いている。
ミーティングルームには重苦しい空気があって、メンバーからの発言や質問は特にない。



これも「あるある」ですね。意見を言いづらい雰囲気、発言しにくい空気感というのは、質問をためらわせますよね。



そうなんですよ。一方的に話されていると感じたり、誰にも意見を求められない状況だと、メンバーは置いてけぼりにされたような気持ちになるでしょうね。



リーダーが「どう思う?」と声をかけてくれるだけでも、全然違いますよね。
持論ばかり語られると、発言のタイミングを見計らうのも難しいですし。



そういうリーダーほど、日頃から相手の話を聞くコミュニケーションが不足している可能性がありそうですね。
定例ミーティングの場で、普段のコミュニケーションのあり方が露呈してしまうのかもしれません。



本当にそうですね。傾聴力や、メンバーに均等に質問するファシリテーション能力が問われますね。



はい、ありがとうございます。
では3つ目です。
そもそもアジェンダが整理されておらず、バラバラと報告事項が読み上げられるだけの会議。
最後に『他に何かありますか?』と投げかけられるが、毎週特に誰も手を挙げないので、いつも早めに解散する。



アジェンダは本当に重要ですよね!
定例ミーティングの基本中の基本だと思います。



アジェンダがない、もしくはその場で共有されるというのは厳しいかもしれません。
メンバーは事前に何を議論するのか想定できないため、準備もできませんし、深い議論もできないですよね。



報告だけで終わってしまうなら、それは会議とは言えないですよね。
会議には様々な目的があるはずです。報告会議という位置づけなら良いかもしれませんが、意見交換や議論は生まれませんよね。



確かに、それぞれの担当者がただ報告するだけで、化学反応は全く起きませんから。会議の意味そのものが問われますね。



では、最後の4つ目。
カレンダー上に予定されてはいるが、上司部下と共に乗り気ではない定例の1on1ミーティング。
今週はちょっとバタバタしているのでという理由で、2回に1回はスキップされている。



あー、これ、僕も自分でやってしまったことがありますね……。



1on1を組んでいたのに、忙しさを理由にスキップしてしまうというのは、よくある光景かもしれません。僕にも身に覚えがあります…。



ええ、「バタバタ」という言葉は、ある意味便利な言い訳ですよね(笑)。
でも、部下からすると、せっかく設けられた時間が上司の都合でなくなるというのは、やるせない気持ちになるでしょうね。



忙しいからこそ、1on1は重要だと思うのですが。時間を取ると決めたなら、よっぽどのことがない限り守りたいですね。
一度予定が流れると、「また来週もどうなるんだろう」という不安感を与え、悪習慣になってしまいます。
お互いに決めた日程を守ることは、信頼関係を築く上でも非常に重要なポイントだと思います。
イケてる定例ミーティングをつくる4つのコツ





さて、4つのダメな定例ミーティング事例をご紹介しましたが
『冒険する組織の作り方』では、イケてる定例ミーティングのコツもたくさん紹介されています。3つご紹介します。
まず1つ目は「開始時に目的をしっかり共有する」ということです。
前回の議論やミーティングの狙いを冒頭で確認し、「何のための会議なのか」「共通のゴールはどこにあるのか」を参加者全員ですり合わせることが重要だと書かれています。



確かにこれはめちゃくちゃ大事ですね!
これをやるかやらないかで、会議の深まり方が全く違ってきます。



はい、続いて2つ目。
「ちょっとしたアイスブレイクを入れる」。
これは「せやまん」の得意分野かもしれませんね(笑)。



いやいや(笑)



書籍にはこうあります。
ミーティングの開始直後は、参加者の意識モードがまだ切り替わっておらず、直前までの作業や打ち合わせをつい気にしてしまうものです。
いきなり本題に入るのではなく、軽いアイスブレイクを挟むようにしましょう。週始めの定例などでは、ちょっとした近況報告やその日の気分などを全員に一言ずつ話してもらうチェックインもおすすめです。
これだけで発言のハードルが下がり、自由に意見が出しやすくなります。



アイスブレイクは、確かに難しい面もありますが、意識的に取り入れるようにしています。
私の今の会社はチームメンバーが一人だけなのですが、毎朝月曜日に朝礼を行い、1週間のタスク整理や重要事項の確認をしています。
ただ、アイスブレークを入れると、どうしても時間が長くなってしまうという課題があります。



そうなんですね!朝礼は何分くらいされているんですか?



ええと、30分取っていて、結果的に2時間になることも……。



おぉ…それは確かに長いですね。経営会議並み(笑)。



そうなんですよー、脱線することが多いんですよ。
でも、そこから新しいアイデアが生まれたりもするので、一概に悪いとは言えないのですが、短くする必要があると感じています。
アイスブレークは、時間を決めてコンパクトに行うのが良さそうですね。



では、3つ目。「問いかけを工夫して意見を引き出す」です。
ファシリテーターから何か意見ありますか?自由に話してください」といった曖昧な問いかけでは、参加者は何を言えばいいのか迷ってしまいます。
人はある程度の制約がある方が考えたり話したりしやすいものです。
「このアイデアはどうですか?」ではなく、「このアイデアは100点満点中何点ですか?」とするなど、みんなが答えやすい問いかけを意識してみましょう



これはすごく重要ですよね。問いかけ方一つで、メンバーからの意見の出やすさや質が大きく変わります。
リーダーやファシリテーターは、メンバーが発言しやすいように工夫し、議論を深める必要があると思います。



問いかけの工夫は、なかなか難しいですよね。ヤマケンさんと話していると、問いかけをしなくても良いアイデアがどんどん出てくるじゃないですか。



嬉しいです!ありがとうございます!でも、それはお互いの良い関係性が影響しているのかもしれませんね。



確かに、職場の雰囲気やリーダーの姿勢も大きく影響しますよね。
同調圧力が強い環境だと、意見は出にくくなりますし。リーダーが否定的な態度を取らず、どんな意見も受け止めて深掘りしていく姿勢が大切だと思います。
イケてる定例ミーティングは良好な人間関係からはじまる





イケてる定例ミーティングのコツを、私も明日からの業務に取り入れていきたいと思います。
やはり、事前に目的やアジェンダを共有すること、アイスブレークを取り入れること、そして、日頃からのチームメンバーとの距離感を縮めておくことが大切ですよね。



まさにそうですね。どんなミーティングも、その前の人間関係が土台となるのだと思います。
壁がある状態では、どんなに工夫しても深い議論はできませんし、チーム作りそのものが、イケてる会議の実現に繋がるのかもしれません。



本当にそうですね。日頃のコミュニケーションの積み重ねが、定例ミーティングの質を大きく左右すると思います。
メンバーの空気感一つで、会議の雰囲気は全く変わりますから。



だからこそ、僕たちが「イケジンRadio」でお届けしているような、面白さやワクワク感を会議の場にも取り入れて、メンバーがリラックスして話せるような雰囲気作りをリーダー自身が心がける必要があるのだと思います。



はい、本当にそうですね。今日はすごく良い話ができました。私も改めて気をつけなければならない点が見つかりました。特にアイスブレークの時間は短くします!(笑)
生産性を意識して、イケてる定例ミーティングを目指していきましょう!



というわけで、今回は『冒険する組織の作り方』から、イケてる定例ミーティングのあり方について語り合いました。
今後もイケジンRadioでは、皆さんの役に立つような面白い人事施策や取り組み、人事の仕事の面白さなどを発信していきますので、次回の放送もお楽しみに!
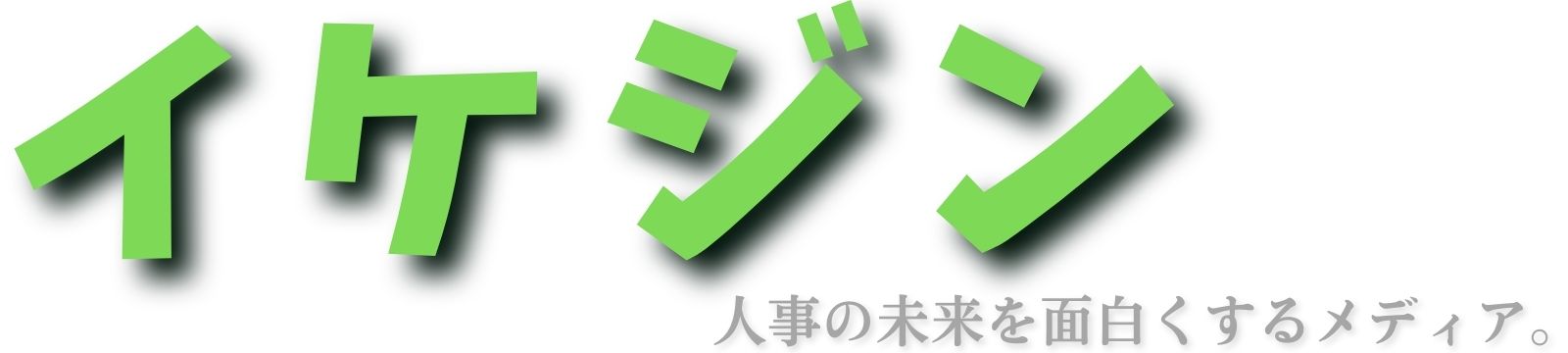

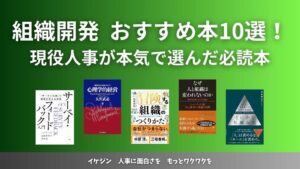



コメント