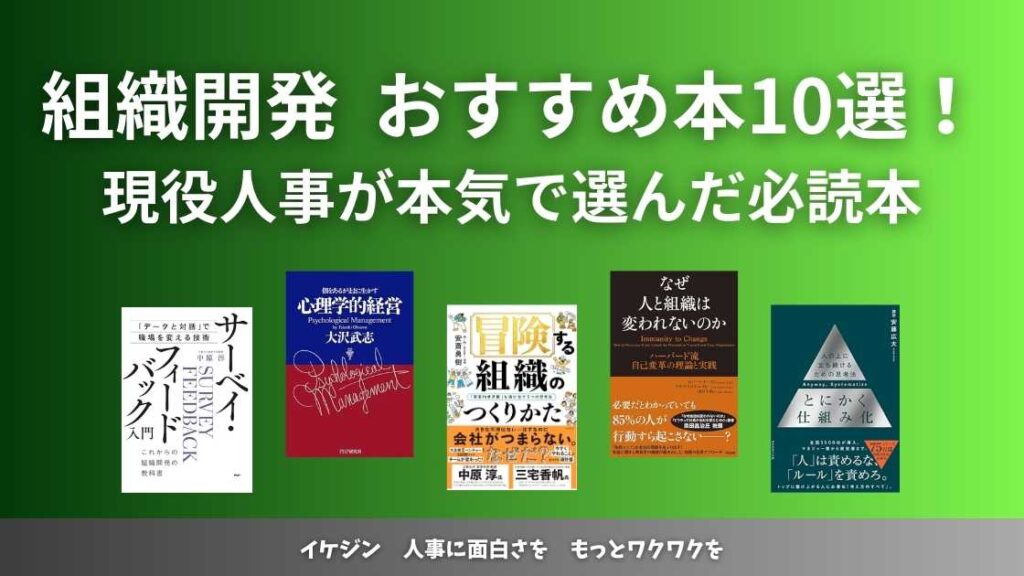
「組織開発って、なんだか難しそう…」そんな印象を持っている方も多いかもしれません。
実際、組織開発に関する本はたくさん出版されていますが、「結局どれから読めばいいの?」と迷ってしまう方も多いはずです。
できれば、時間をかけずに効率よく学びたい。そんな方のために、今回は組織開発の基本から実践までがしっかり学べる名著10冊を、現役人事の視点から厳選してご紹介します。
組織開発とは?

組織開発(OD:Organization Development)とは、組織に関わる「人」と「関係性」に働きかけながら、個人・チーム・組織全体の力を引き出し、持続的な成長を目指す取り組みです。
単なる制度設計やルールづくりではなく、「なぜ成果が出ないのか」「なぜ組織が動かないのか」といった目に見えづらい課題を丁寧に紐解き、より良い状態へと導くことが目的です。
たとえば、以下のようなテーマが組織開発に含まれます。
- 組織の課題を可視化するためのサーベイや対話
- チーム間の信頼関係を築くワークショップ
- 変化に強い風土を育むリーダーシップ開発
- メンバーの力を引き出すフィードバックや1on1
- 働く人が主体的に動ける仕組みの設計
事業が成長するには、組織の土台も一緒に育っていく必要があります。
組織開発は「人事の仕事」と思われがちですが、実は経営の中核にあるべきもの。組織が変われば、事業も変わる。その大きな変化を生み出すカギが、組織開発にはあるのです。
組織開発のおすすめ本10選!現役人事が本気で選んだ必読本
組織と働き方の本質 迫る社会的要請に振り回されない視座
人的資本、ダイバーシティ、ジョブ型。いま企業が直面する「社会的要請」にどう応えるべきか。
本書『組織と働き方の本質』は、その問いに「振り回されず、立ち止まって考えよう」と指摘しています。
トレンド的なバズワードを鵜呑みにする前に、本書では組織の本質やマネジメントの役割を問い直す視点が書かれており、読めば読むほど、自社の取り組みを俯瞰して見直したくなる内容です。
「働く個人は投資家である」という視点も秀逸で、社員との関係性を再定義するヒントが詰まっています。
人事・経営層はもちろん、これからの働き方に悩むすべての人におすすめです。
冒険する組織のつくりかた
『冒険する組織のつくりかた』は、目標があっても人が動かない、チームはあるのにつながりが浅い、そんな「組織のズレ」に悩んでいる人事こそ読むべき一冊です。
従来のトップダウンな「軍隊的な組織」から脱却し、心理的安全性・自己開示・学習文化をベースにした「冒険的組織」への転換を、豊富な事例と実践メソッドで解説。
数値目標やMVVも社員に「腹落ち」してこそ意味がある。制度先行ばかりで空回りする企業にとっては、まさに気づきばかりの一冊。
現場のモヤモヤを言語化し、対話・納得・自律で組織を変える力が湧いてくる、実践知に満ちた良書です。経営者・人事・マネジャー・リーダーにとっての必読書です。
とにかく仕組み化 人の上に立ち続けるための思考法
『とにかく仕組み化』は、「なぜ人は動かないのか?」に悩む人事担当者にこそ読んでほしい一冊です。
属人化ではなく仕組み化で解決するという明快なメッセージは、制度設計や人材育成に関わるすべての場面に通じます。
ミスや混乱が起きたとき、「人を責めるな、ルールを責めろ」という考え方は、人事にとって非常に実用的な視座です。
また、従業員が「進行感」を感じられる仕組みづくりの重要性も説かれており、エンゲージメント向上のヒントが詰まっています。
現場任せのマネジメントから脱却し、仕組みで強い組織をつくる人事の実務に、確かな武器となる一冊です。
だから僕たちは組織を変えていける
『だから僕たちは、組織を変えていける』は、人事の立場で「現場が動かない」「心理的安全性が根づかない」と悩んでいる方にこそ届いてほしい一冊です。
数字や施策で管理する従来の手法ではなく、関係性→思考→行動という「成功循環」を通じて、組織の内側から変革を促す実践論が詰まっています。
心理的安全性、内発的動機、意味づけなどの理論を、現場目線で使える形に整理しており、「まず誰と、どう関わるか」から組織開発を始める視点が得られます。
人事制度や研修だけでなく、“空気を変える力”を求める人事の方に強くおすすめします。
ビジョナリー・カンパニー3 衰退の五段階
『ビジョナリー・カンパニー3 衰退の五段階』は、組織の「衰え」が静かに始まる構造を明らかにした一冊です。
人事にとって特に示唆的なのは、「成功から生まれる傲慢」「問題の否認」「一発逆転の幻想」といったプロセスが、いかに組織文化を蝕んでいくかという視点。
制度や人材開発が機能しなくなるのは、仕組みの前に「意識」が衰退しているサインかもしれません。
変化そのものが価値ではなく、原点への回帰こそが再生の鍵。
人事として組織の健康診断を担う立場にある方に、必読の一冊です。
図解でわかる! 形骸化させない 研修体系とスキルマップのつくりかた
『図解でわかる!形骸化させない 研修体系とスキルマップのつくりかた』は、「研修はしているけれど、育成につながっていない…」と感じている人事にとって、まさに処方箋となる一冊です。
Off-JTとOJTをどうつなぎ、現場で活かすのか。その鍵となるのが「求める人材像」と「スキルマップ」の設計。
本書では、育成方針の立て方から運用・改善のサイクルまで、図解を交えて実践的に解説されています。人的資本経営が注目される今、人材育成の仕組みを見直すきっかけにぴったりの実務書です。
現場を動かす育成を目指すすべての人事担当者におすすめします。
なぜ人と組織は変われないのか
『なぜ人と組織は変われないのか』は、変革が進まない理由を「仕組み」ではなく「心の防衛反応」に切り込んだ一冊です。
行動が変わらないのは意志が弱いからではなく、無意識のうちに「変化から自分を守っている」から。
本書が提唱する「免疫マップ」は、変化を阻む裏の心理構造を見える化し、真のブレーキを外すための実践的アプローチです。
人事として制度を整えても現場が動かないと感じている方、育成や組織開発で本当の変化を起こしたい方にこそ読んでほしい一冊。
変わらない理由が、きっと変わる希望に変わります。
サーベイ・フィードバック入門
『サーベイ・フィードバック入門』は、「サーベイをとって終わり」になってしまう人事施策に悩む方にこそ読んでほしい一冊です。
組織調査(サーベイ)で現状を「見える化」し、対話を通じてチームの行動変容へとつなげる。このプロセスが、組織を本質的に変える鍵になります。
HRテックやエンゲージメント調査を導入しても活用に悩む企業は多い中、データの“読み方”だけでなく「届け方」まで丁寧に解説している点が秀逸。
図解や事例も豊富で、人事だけでなく現場マネジャーにも実践しやすい内容です。「データと対話で組織を変える」新しい教科書としておすすめです。
心理学的経営 個をあるがままに生かす
『心理学的経営 個をあるがままに生かす』は、「人を活かすとは何か?」を本質から問い直す一冊です。
制度や管理だけでは人は動かない。リクルートでの実践と心理学の理論をもとに、「個性化」と「活性化」のマネジメントを解き明かします。
自己理解なくして他者理解なし、という視点は、まさに人事が持つべき原点。
動機づけ理論や組織風土、無意識の影響にまで迫る本書は、形だけの人材施策に限界を感じている人事担当者に強くおすすめです。
30年経った今こそ、再び読みたい「人間中心の経営」の教科書です。
図解 組織開発入門
『図解 組織開発入門』は、「組織開発って何から学べばいいの?」と迷う人事担当者のための道しるべです。
理論だけでなく現場目線で構成されており、対話・サーベイ・学習する組織など、注目テーマを網羅。各章は図解とQ&A付きで、必要なところから読める親切な設計です。
「組織に血を通わせる」ために、人材マネジメントの「型」を超えて「あり方」を考える。そんな本質的な問いに寄り添ってくれる一冊。
人事・マネジャー・経営層まで、すべての「組織を動かす人」におすすめです。
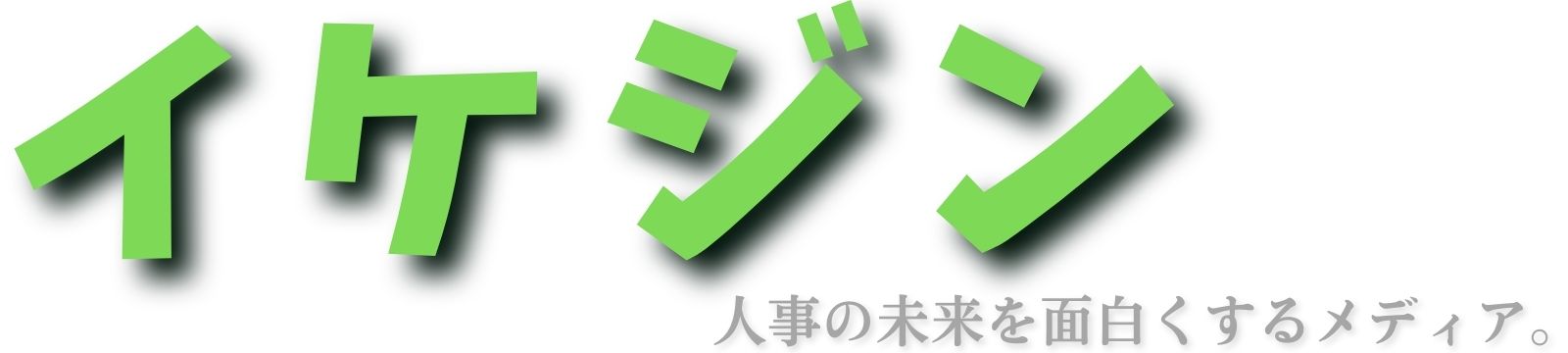












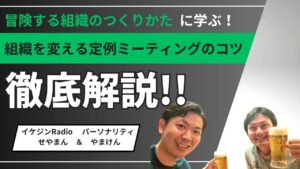


コメント